「もう年だから」「今さら無理かも」―。誰もが一度は抱く不安と戦いながら、新しいことに踏み出すのを躊躇した経験があるのではないでしょうか。私も50代でありながら、長年の夢だった大型自動二輪免許の取得に挑戦するまで、そんな思いと向き合い続けていました。
挑戦せずにいては現状から何も変わらないこと
体力面での不安や技術習得への不透明感
当ブログでは、これまで教習日記を通して、等身大の姿で悩みや成長の過程を共有してきました。その集大成として、いよいよ卒業検定に挑んだ経験を綴っています。
卒業検定での課題とその克服方法、そして何より「挑戦する勇気」の大切さについてお伝えします。
この記事を読むことで、大型自動二輪免許の取得を目指す方はもちろん、年齢を理由に夢を諦めかけている方々の背中を押すきっかけになれば幸いです。
「人生に遅すぎるなんてことはない」「今日が人生で一番若い日」その証明として、私の挑戦の軌跡をご覧ください。
大型自動二輪教習の集大成、50歳にして新たに旅立つための最終試験、卒業検定の様子です。さて、緊張と興奮の検定当日は・・・
※普通自動二輪(中型自動二輪)免許保有者が教習所に通って大型自動二輪免許MTを取る前提です。

卒業検定のポイント
- 3人ごとのチームに分かれて検定を受けます
- 検定コースは2コースあり、どちらになるか当日発表されます
- 検定が終わると教官から講評を聞きます
- 合格していれば卒業式で卒業証書が授与されます
卒業検定コースと採点基準
卒業検定コース
私が通った教習所の卒業検定コースは2つあります。それぞれ課題が前半と後半に分かれていて、前後の課題を丸ごと入れ替えることで、2つのコースが設定されている仕組みです。さらに、大型自動二輪ですのでコースの最後に「波状路」が加えられています。
※教習所によりコース順は異なりますので、ご参考までに
- 卒業検定1コース
発着点 → (坂 → スラローム → 平均台) → (踏切 → Sコース → クランク → 左折可 → 急制動) → 波状路 → 発着点 - 卒業検定2コース
発着点 → 外周 → (踏切 → Sコース → クランク → 左折可 → 急制動) → (坂 → スラローム → 平均台) → 波状路 → 発着点
各課題の内容と採点基準
基本的な採点の仕組み
- 持ち点100点からの減点方式
- 減点累積30点以上(70点未満)で不合格 → 30点までの減点であれば合格
大型自動二輪の卒業検定は、持ち点100点からの減点方式で採点されます。各課題の評価で減点が累積し、30点を超える、つまり持ち点が70点を下回ると不合格となります。裏を返せば、減点が30点以内であれば合格できるということです。「少々減点しても大丈夫!」と自分に言い聞かせ、落ち着いて検定に臨むことが大切です。
即時不合格(一発不合格)となる主な項目
- パイロンとの衝突(スラローム、クランク)
- コースからの逸脱(平均台で脱輪、クランクやS字でコース外れ)
※これらは点数に関係なく、その時点で試験中止
点数に関係なく一発不合格となるケースもあります。課題ごとに設定されており、主な例としてパイロンとの衝突(軽い接触は減点)やコースからの逸脱が挙げられます。私が検定を受けたときも、途中で試験が中止になってしまった方がいました。
目標タイムと減点
| 課題 | 目標タイム | 減点(1秒につき) |
|---|---|---|
| スラローム | 7秒以内 | 5点 |
| 平均台 一本橋 | 10秒以上 | 5点 |
| 波状路 | 5秒以内 | 5点 |
卒業検定では、いくつかの課題に目標タイムが設定されています。目標タイムを上回ったり下回ったりした場合、1秒ごとに減点される仕組みです。しかし、タイムを気にしすぎるのは禁物です。特に平均台(一本橋)で脱輪してしまうと、即座に検定が中止になってしまいます。減点は多少あっても、課題を確実にクリアするほうが合格の可能性を高める結果につながります。
卒業検定では「安定した走行」を最優先に心がけましょう。例えば平均台では、ゆっくり慎重に進むことが重要です。無理にタイムを稼ごうとしてバランスを崩してしまうと、結果的に大きなミスにつながります。またスラロームでは、リズムよく走行することがポイントですが、速度を意識するあまりコーンに接触すると減点対象になるため注意が必要です。
検定を通過するためには、「タイム」よりも「正確で安定した操作」が鍵です。焦らず、落ち着いて取り組みましょう。
卒業検定
卒業検定 当日
最後の教習から2週間の間隔が空いてしまい、バイクの感覚はこれまで以上に忘れてしまっているかもしれません。
今にも雨が降りそうな曇り空、検定中に雨が降るかもしれない予報。雨なら急制動は通常より遠い停止位置になるので、それならラッキーであるとも言えます。
教習所で受付を済ませると、控室となる教室に行くように指示されました。検定を受ける生徒が集まってきますが、特に話すこともなく、乗車までの手順のビデオが繰り返し流れています。ずっと同じ内容なので、検定コースを確認することにしました。
こういう日に限って、仏壇に手を合わせなかったことを思い出します。そっと見守っていてほしいと思うばかりです。
教官が来られ、まずは教室で試験の注意点などの説明を受けます。最後に検定員の名前と自分のゼッケンをもらいました。6チームに分けられ、私の検定の順番がチーム内で1番目となりました。前の人を見てコースをおさらいしようかと思っていましたが、まさか1番になるとは。2つある卒業検定コースの内、外周から踏切を通る2コースで検定をすることが発表されました。
教室を出て、全員でコース横の教習控室に向かい準備をします。いつも通り、膝、肘、胸部のプロテクターをつけ、今回は検定中と書かれたゼッケンをその上からつけます。 名前を呼ばれて教習原簿と免許証を見せると、準備ができたら試験を始めるとのことです。練習走行もなく、一番目ということで緊張が増していきます。心拍数が高くなるのがわかり、いい歳して緊張するものだと感じました。
教官は緊張をほぐすために丁寧に話しかけてくれ、深呼吸をするように促してくれました。小雨が降ったり止んだりしており、コースはウエットと判断されました。そのため、急制動の停止位置が長くなりました。
卒業検定 前半
検定開始です。後方確認を行い、スタンドを払ってから乗車します。ミラーを合わせ、ニュートラルを確認してからエンジンをかけます。発進は自分のタイミングで行うことになっているので、ここで落ち着いて周囲を確認し、発車しました。
106号車はこれまでの教習車とは異なり、すこぶる調子が良い車体です。発進してからチェンジを変え、すぐにセカンドに入れることができました。検定でいいバイクが当たって良かったと思います。
外周・踏切
外周を回り、右折し左折して踏切に向かいます。踏切前で一時停止し、左右を確認して音を聞きます。もちろん何も来ないのですが、大きく首を振って確認します。約30年前の教習では、しっかり確認しないと叱られたことを思い出します。一速であることを確認して発車し、外周に出るには少し見通しが悪いので、ゆっくり進んで確認します。
左折し外周を少し走った後、再び左折してコース中央の交差点を通過します。次の交差点を左折するので、ウインカーを出し、後方確認をしてからバイクを左側に寄せます。その後、外周を少し走ってからS字に向かいます。
S字
前回の走行から時間が空いたため、バイクを左右に振り回すのがぎこちなく、自分でもニーグリップが甘いことがよくわかります。左、右とバイクを走らせて無事に通過しました。外周を走りクランクに向かいます。
クランク
クランクの手前には交差点があるため、早すぎるウインカーは避け、交差点を過ぎてからウインカーを出し、左後方を確認してバイクを左に寄せます。二つあるクランクのうち、どちらも空いていたので奥のクランクを選びました。一つ目の角はすぐに曲がる必要がありますが、出口に余裕ができるので落ち着けると感じました。ふらふらしていることは自分でもわかりますが、なんとか通過しました。
左折可
中央の左折可のある交差点で左折し、見通しの悪い交差点で一時停止します。一速を確認し、少し前進してさらに確認します。通過車両もなく外周を左に出て、バイクを左に寄せて交差点を左折し、中央交差点を右折して急制動に向かいます。
急制動
バイクの調子はすこぶる良いです。加速もスムーズで、シフトアップも難なく行えます。急制動の一つ手前の直線で三速にシフトアップし、コーナーを曲がって最後の直線で一気に加速します。40キロが出ていることを確認し、アクセルを戻して惰性で走ります。制動開始位置を過ぎてから前後のブレーキを強くかけます。停止位置はウエットなので奥になりますが、ここで「しまった!」と思いました。癖で、クラッチを早々に切ってしまいました。あっ、と思いましたが、やり直すわけにはいきません。止まったので、まあ良しとし、次の課題である坂道発進へ向かいます。これで前半が終了しました。
卒業検定 後半
坂道
急制動の停止位置から右に寄せ、交差点を右に曲がります。坂道手前の中央交差点を過ぎた後、左に寄ります。坂道は3レーン全てが空いています。そこで、真ん中の2レーンに入ることにしました。停止位置に止まり、ギアを一速に入れます。後方を確認し、クラッチを放しながらアクセルを少し開けます。後ろブレーキを緩めると、バイクがスッと前に出ます。坂道の頂上を過ぎた後、エンジンブレーキをかけながら下り、「止まれ」の表示に従います。左右を確認し、右からバイクが一台来たのでやり過ごしてから左に発進し、スラロームへ向かいます。
スラローム
坂道出口の横にスラロームの入口があるため、左回りでぐるっと一周してからスラロームに入るのが決まりです。中央交差点で信号待ちをしているバイクが一台いたので、少し後ろで止まりました。ネットでも言われているように、検定中の信号待ちは一息つくのにちょうどいいです。適度なスピードでスラロームに進入しました。左右にバイクを振りながら進みますが、ここでもニーグリップが甘いことを実感します。パイロンには当たらず無事に通過しました。出口で右からバイクが来たので、念のため停止しました。どちらかと言えば、自分の心を抑えるために止まったようなものです。次は平均台です。
平均台(一本橋)
平均台はスラロームの出口の横に入口があるため、こちらも左回りでぐるっと一周します。平均台には2レーンあり、右側の方が停止線が道から少し距離が離れています。そのため、バイクを平均台に対して直線的に合わせやすいようになっています。これもラッキーでした。自分の中では最大の難関で、16歳の時には一度も落ちたことがない平均台ですが、50歳になった今は何度も落ちてしまいました。正直、不安と少しの恐怖心が拭えません。教官の教え通り深呼吸をしてみます。そして少し時間を取りました。不安が完全になくなるわけではありませんが、行くしかありません。一速であることを確認し、ウインカーを右に入れて発進します。よし、乗れました。あとはバランスとスピードのコントロールだけです。落ちないようにと、真ん中くらいまでは一気に進みました。今日は行けそうだと感じます。そこからリアブレーキを使いながらスピードを調整していきます。今日は行けそうだと感じたので、いい頃合いだと思いバイクを進めました。平均台を無事に通過することができました。次は最後の課題、波状路へ向かいます。
波状路
平均台から右に曲がり、外周を半周します。奥の交差点から右折して中央交差点へ向かいます。そこで教官から停止の指示がありました。前車が波状路に入るため、交差点で止まるようにとの指示だったのです。信号が変わるタイミングで発進し、左に寄せて波状路に入ります。スタンディングで進行しながらウインカーを右に出します。深く考えずに通過することができました。左右を確認し、発着点に向かいます。左ウインカーを出して左に寄せ、無事に発着点に停止しました。ニュートラルに入れ、エンジンを切って下車します。スタンドを出してバイクをしっかり傾け、ハンドルを切ります。何とか完走し、無事に終了することができました。
講評
教官から講評をいただきました。まずはタイムについてです。
- スラローム: 8.4秒 目標タイムに対して1.4秒オーバー
- 平均台: 8.6秒 目標タイムに対して1.4秒ショート
- 波状路: 7.8秒 目標タイムをクリア
減点は覚悟していましたが、平均台がショートしていたとは驚きました。10秒というのは長いと感じましたが、無事に通過できたことが何よりも大事です。
久しぶりにバイクに乗ったため、ぎこちない運転を教官はしっかり見抜いていました。スラロームについては、車体を傾けるのではなくハンドルを切って曲がっていると指摘されました。その通りです。練習で最高だったときの感覚、スムーズに左右に車体を傾けて通過する本来のスラロームとはかけ離れた操作感でした。通過することやパイロンに当てないことばかりに気を取られていました。他には特に大きな指摘はなく、終了となりました。
終わってしまうと気楽なものです。早速先輩のように振る舞い、他の受験者の走行を見守ることにしました。中にはコースを間違える人、平均台から落ちて検定中止となる人、ギアが入らず大きく空ぶかしする人など、様々な場面が見られました。自分がそうなっていたらと思うとゾッとする思いです。また、気にしていた左右の確認も、不十分な人が多いようでした。減点にならなければいいですが。
全員の検定が終わり、別の教室に移動するよう指示が出ました。
卒業式
教室には「卒業式会場」と書かれており、その準備が整っていました。この時点では合否がわからないにもかかわらず、さっさとアンケートを回答する人がいることに驚きました。自信があったのでしょうか。
その後、偉い方が来ていろいろと説明を始めました。合否の確認のために一旦離席されると、私はそれなりに自信を持ちつつも、一抹の不安がありました。あの走りでは、大きな減点も覚悟しました。
しばらくして、担当者が合否を持って戻ってきました。1人ずつ名前を呼ばれ、合否が伝えられます。名前が呼ばれ、「合格です」と言われた瞬間、ほっとしました。続けて他の受験生の名前と合否が伝えられました。最後の方まで呼ばれ、そこにいた全員が合格でした。
卒業証書が1人ずつ渡され、卒業検定当日の予定は全てが終了しました。
教習を修了して
全般として、とても印象の良い教官と教習でした。この30年で方針が大きく変わったのか、時代の流れがそうさせたのか、とてもフレンドリーに若者から年長者まで同じレベルで指導しているように感じました。指導も的確でわかりやすかったです。敢えて気になる点を挙げるとすれば、優しさを超えて甘すぎるのではないかということです。
後でわかったのですが、周囲への確認が不十分だと感じる受験生は現役ライダーだったようです。一般道での癖をそのまま教習所で持ち込んでいたのでしょう。教習所だけで真面目な運転をしろとは言いませんが、せっかく間違った癖を直すチャンスだったのに、教官が指導や指摘しなかったことには残念に感じました。
年齢的にも補講はやむなしと考えていましたが、一度も補講を受けることなく、最短の12時間で教習を終え、検定も1回で合格できました。初めて教習車に乗ったときに「行ける」と感じたのが一番良かったのかもしれません。体力や反射神経は落ちていると予測しましたが、バイクを走らせることに問題はなく、自信につながったと考えています。真夏の教習で汗だくにもなりましたが、風を切って走ることで、若い頃の楽しかった感覚を再び味わえたことが何より良かったです。
近いうちに試験場へ出向き、新しい免許証の交付を受ける予定です。もうすぐ始まる第二のバイクライフを存分に楽しみたいと思います。
免許証発行
卒業検定を無事に合格してから3日が経ちました。仕事の都合で平日に休みを取ることができたため、運転試験場で免許証の内容を書き換える手続きを行いました。隣接の駐車場が空いていたので車を止めましたが、結果的には民間の駐車場の方が安かったかもしれません。受付で書類を2枚書き、2回お金を支払いました。写真撮影は1時間半後と言われたので、ぶらぶらしようかとも考えましたが、いつも献血をしていることを思い出し、今回も献血をすることにしました。時間を有効に使いつつ、世の中の役に立てるのは良いことだと思います。
とはいえ、献血もそれほど時間がかからなかったため、結局待合室で待つことになりました。写真を撮るだけなのに、なぜか緊張してしまいます。一番気になるのはやはり写真写りですよね。どうしても人相が悪く見えてしまうのは、なぜなのでしょうか。
時間になり、写真撮影を行いました。一応鏡で髪型を整えてみましたが、あまり変わらず、流れのままカメラの前で着席しました。前回の写真は家族にも評判が良くなかったので、今回は特に目を見開くこともなく、自然な表情で撮影しました。今回も眼鏡等の条件には当てはまりませんでしたが、写真は眼鏡をかけた状態で撮影しました。視力も限界に近いので、普段から眼鏡をかけて運転していますが、免許証にもその旨を記載してもらった方が良いかもしれないと思いました。
さて、気になる写真の出来栄えですが、可もなく不可もなく、といったところでしょうか。今回はそれほど人相が悪く見えないのではないかと思います。そして、ついに免許証に「大自ニ」の文字が追加されました。普自ニが書き換わるのかと思っていましたが、その左横に新たに追加される形でした。
これで晴れて大型二輪ライダーとなりました。免許を取る前、さらには卒検に合格する前に、バイクの契約を済ませてしまいましたが、まだまだ準備が整っていません。グローブはまだ用意しておらず、プロテクター付きのアウターも必要です。ブーツはどうするか、バイクカバーも目星をつけていません。やることは山積みです。
まとめ

34年ぶりに受けた二輪の卒業検定でした。
年甲斐になく緊張したり不安を感じるのは、これまで経験からくる防御反応みたいなものなのでしょうか。年を取ると「失敗できない」とか「恥をかけない」などの感情が先に出てきてしまします。それが経験なんですが、それが新しい道への第一歩をためらわせているに違いありません。
一歩踏み出した先にしか、その先がありません。
そして何より楽しかったです。
新しく学ぶこと
新しく体験すること
新しい場所に行くこと
新しい経験が少なくなってくる年代に、新しい挑戦ができたことはこの上なく心を満足させてくれました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。お役立ち情報やマル秘テクニックなどはないブログですが、50歳の等身大の挑戦記になったと思います。
ご同輩諸君、少しずつ手が空きはじめ、お金はないけど時間はある、待ちに待ったときが来ました。様々なことにチャレンジして更に充実した人生にしていきましょう。
「今日が人生で一番若い日」ですよ。
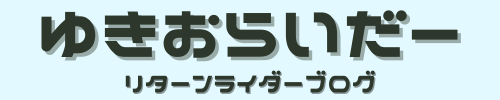




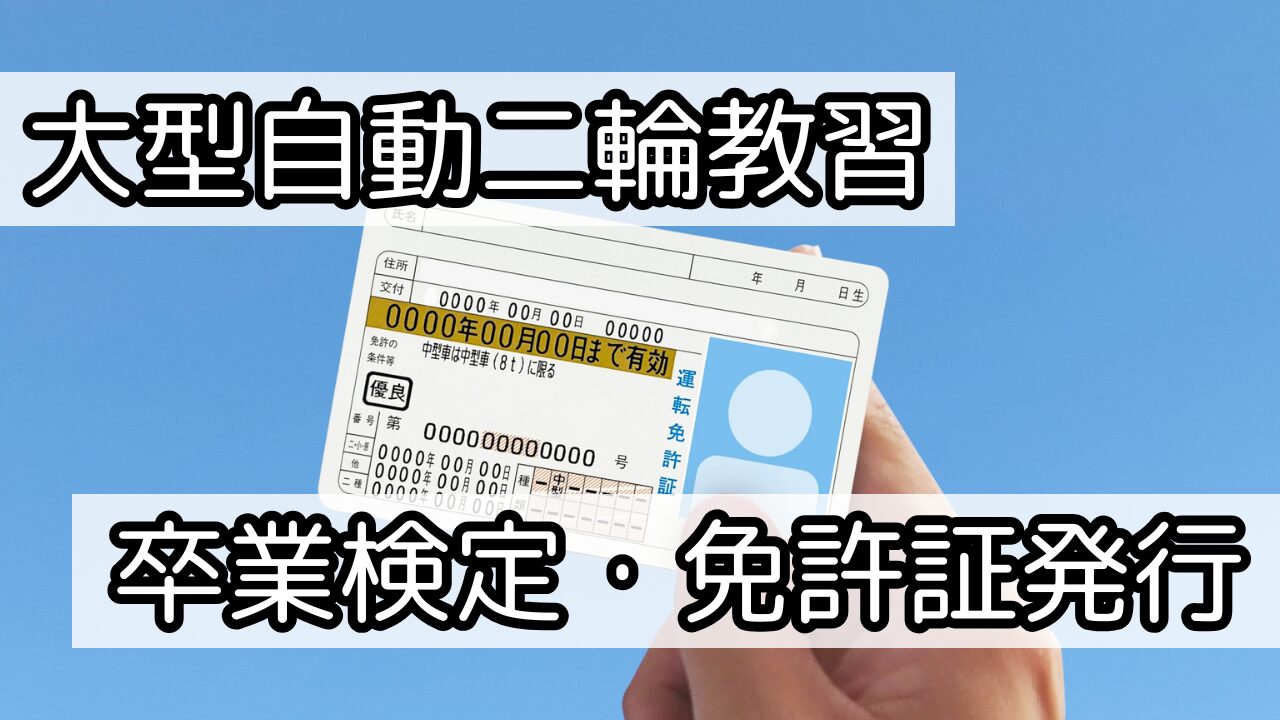

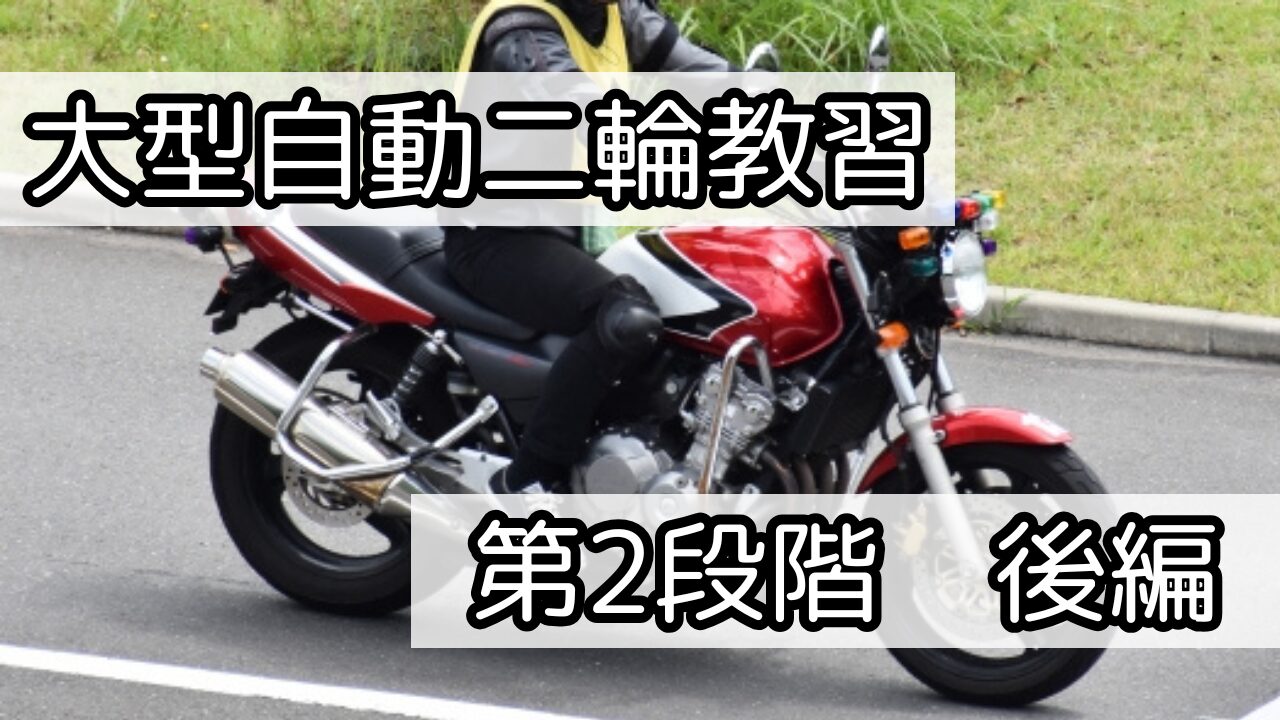
コメント